非課税世帯への3万円給付と「取って配る」式の非効率
住民税非課税世帯への3万円支給が始まるようですが、これがずいぶんと非効率です。支給対象が「令和6年度住民税非課税世帯」であるため、各自治体ではその支給対象世帯を特定するなどの無駄な作業を強いられることになるだけでなく、支給対象世帯とそうでない世帯との間に分断と対決を生みかねないものでもあります。こうした「取って配る」が行き過ぎれば、それは行政の無駄と断じざるを得ないでしょう。
3万円給付事業は「取って配る」の典型例
行政の無駄は「取って配る」に尽きます。
役所はとにかく税金を「取る」ことが大好きであるとともに、取った税金を「配る」こともまた大好きなようです。
もちろん、行政である以上はある程度、「取って配る」(たとえば所得の再配分)などが生じるのは仕方がない話ですが、それが行き過ぎれば有害です。全国で恐ろしい行政の非効率を生む可能性があるからです。
その典型例が、低所得層などに対する3万円の給付ではないでしょうか。
「3万円給付」については先日、『くらしとお金の経済メディア LIMO』というサイトに、対象となる人や給付金の申請方法などの解説が掲載されていました。
【最新情報】住民税非課税世帯への3万円給付が続々とスタート。ところで対象となるのはどんな人?
―――2025.02.10 18:10付 LIMO くらしとお金の経済メディア より
支援事業の概要
リンク先記事はウェブページ換算で4ページにわたるものですが、要約するとこんな具合です。
- 政府は昨年、物価高対策として住民税非課税世帯に対し1世帯当たり3万円の給付を決定した
- 子育て世帯には子供1人につき2万円が加算される
- 各自治体が支給を担当し、2025年1月から順次実施されている
- 対象世帯は自治体により異なるため居住地の自治体ウェブサイトで詳細の確認が必要
- 申請方法は自治体から送付される書類により異なるほか、追加書類の提出が求められることも
- 支給には審査を含め1ヵ月程度を要するため、早めの手続きが望ましい
この事業自体、「政府が決めた」のではなく、「国会で可決された補正予算に基づいて」事業が実施されている、といった細かいツッコミどころはありますが、この点は脇に置くことにしましょう。
趣旨としては、食料品、エネルギーなどの物価高の影響に対し、賃上げなどでは賄いきれない部分をカバーするものとして、低所得世帯への支援として決定されたものだとしています。
また、対象となる世帯(または対象となる可能性のある世帯)には「支給のお知らせ」と「確認書」、「申請書」の3種類の書類が送られるそうですが、これは支給条件を満たしているかどうかなどが判明していない世帯があるためだそうです。
支給対象の特定などに膨大な事務費が…!
なかなかに、強烈な事業です。
そもそも支給対象となる世帯が「令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯」などの要件を満たしている場合なのですが、各自治体は支給対象者がこの要件を満たしているかどうかを確認しなければならず、これだけでもそこそこの手間がかかると見込まれます。
当然のことながら、使う公金は支給される金額だけではありません。
昨年12月17日付で内閣府地方創生推進室が各自治体に向けて発信した『事務連絡』によると、政府から各自治体に対し、次の算式で計算した金額を上限に、事務費が支給されるようです。
令和6年度非課税世帯数×2,500円+こども加算支援世帯数×2,500円+不足額給付支援者数×3,000円
仮に非課税世帯数が日本全体で1000万世帯だったとすれば、この1000万世帯に3万円ずつ支給するだけで3000億円、これに各自治体への事務費として250億円が必要となる、という計算です。
支給対象、あるいはその可能性がある各世帯に配られる書面が複雑であるというのもうんざりしますが、それだけ事務が複雑だ、ということの裏返しでもあるのでしょう。
支援するなら「減税」が手っ取り早い!
仮に―――あくまでも「仮に」、ですが―――、これを「住民税非課税世帯」ではなく、「全世帯一律」で実施したならば、どうでしょうか。
給付対象の世帯が増えればそれを給付するための費用は増えますし、また、銀行口座と各住民の情報を紐づけなければならないなどの手間は生じますが、少なくとも、各自治体において「非課税世帯を特定する」という無駄な作業はなくなります。
しかし、現金を配るのであれば、もっともっと効率の良い方法があります。
じつは、その秘策とは、
「減税」
です。
「取って配る」とは真逆の発想ですが、「取って配る」くらいなら「最初から取らない」というのが、じつは最も有効なソリューションのひとつではないでしょうか。
ちなみに食品、エネルギー価格などの上昇で苦しんでいるのは、低所得層だけではありません。中・高所得層だって、生活コストの上昇でかなり苦労をしているわけです。
当然のことながら、電気代の上昇に対しては原発の再稼働や新増設はどんどんと進めていただく必要があるわけですが、それだけではありません。
そもそも食品、エネルギーなど世の中のほとんどの項目に課せられている消費税という税金が、生活の重しとなっていることも間違いなく、生活の対する支援というのであれば、消費税の減税(たとえば食品・エネルギー・生活必需品などに対するゼロ%軽減税率の導入)が最も手っ取り早いのではないでしょうか。
あるいは、15歳以下の扶養親族に関する年少扶養控除が民主党政権時代に廃止された影響で、とりわけ現役世代の税負担が重くなっている現状を考えるならば、基礎控除や扶養控除などの復活・拡充などにより所得税負担を軽減することも必要かもしれません。
それなのに、なぜ、①「取って配る」という非効率を好むのか、そして②低所得者に限定した支援しかなされないのか、については、疑問としか言いようがないのです。
税の負担と給付の適正化が必要だ
ちなみにわが国は近年、過去最高の税収を毎年のように記録し、巨額の剰余金を毎年のように計上している状況にあります(『財源論者に不都合な事実…来年度税収見通しは過去最高』等参照)。
言い換えれば、明らかに税金を「取り過ぎている」わけです。
こうしたなかで、「低所得者層」、「住民税非課税世帯」を対象にした支援事業の実施は、無駄に事務費がかさむだけでなく、不公平感から国民の間で不要な分断と対決を生み出しかねない愚策と断じざるを得ないのではないでしょうか。
いずれにせよ、税負担と給付のバランスの適正化はやはり必要であり、それができる政党が今後、大きく躍進していかざるを得ない、などと思う次第です。
本文は以上です。
金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。
日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。
読者コメント欄はこのあとに続きます(コメントに当たって著名人等を呼び捨てにするなどのものは禁止します)。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。
読者コメント一覧
※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。
やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。
※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。
※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。
当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。また、著名人などを呼び捨てにするなどのコメントも控えてください。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。
コメントを残す
【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました
 | 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |
【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました
 | 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |



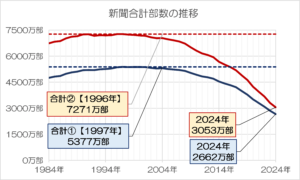
またバラマキが始まるのですね。
非課税世帯って年金受給や生活保護世帯じゃないの?
まじめに働いている人たちからの搾取を減らす方向には行かないようですね。
でも私は所得税や法人税などの減税は大賛成ですが、消費税の減税あるいは撤廃は反対です。
理由は、街にこれでもかというほど溢れるようになったインバウンドに対しても減税となってしまうからです。
私も真っ先に浮かんだのが「年金受給や生活保護世帯」であり、思考の向かう先はインバウンドでした。
>>趣旨としては、食料品、エネルギーなどの物価高の影響に対し、
>>賃上げなどでは賄いきれない部分をカバーする
というのが主旨ならば、年金受給者(生保は割愛w)に対しては複雑な手続きなど踏まずに、さくっと支給額を3万円増やせばいい。財源は税金でいい。
結論から言うと、これこそが「破綻しない」年金です。
根拠はインバウンドです。
サラダ食べて税金とチップを払って10ドルっていう国から来た人たちが「日本だと3〜4ドルで食える」って驚愕(驚喜)しています。
為替レートのことは無視しても、日本の食費は2倍になりレストランのバイト代もまた2倍になっておかしくない。
今日明日の話じゃないけど遠からずそうなっても驚くべきではないと考えます。
その昔「夢のハワイ旅行」なんてワードがありましたが、今のままではバイト代を貯めてハワイ旅行なんて夢のまた夢です。
以下、蛇足ですが「年金」と「破綻」について書きます。
年金は将来必ず破綻するぞ!と言われますがこれは嘘です。
すでに何度も破綻しています。
まず年金の「説明」が破綻しました。
現役時代に積み立てておき定年後に引き出して使えますよ、という大昔の説明で納得できる人はほとんどいないでしょう。
次に年金の「システム」が破綻しました。
60歳から使えますよという貯蓄なり投資商品なりが、「ごめん、あと5年待って」って言うのは大事件です。破綻です。
「さらに5年延長ね」なんて言ってる人も(どこかが)破綻しています。
もう一つ、現役世代が納付したものを(運用で増やして)退職世代に配るというシステムも破綻に向かっています。言うまでもなく少子高齢化だからです。
運用なんてものは仮に失敗して減ろうが破綻ではなく、相場の常。これを織り込むなら破綻気味のシステムとは言えます。
さて、それでも起こしてはならないのが年金「額」の破綻です。
いわば「年金」そのものですが、これを破綻させるようでは政治家も官僚も国民もメディア()も失格です。
私は税金から補填して満足な額にする以外、手はないと考えます。
(なんならたくさん納付した人に、より多く補填するべきとも思う)
だから「年金は払っておけよ」と。
「でも破綻するんでしょ?」と言われたら「何度もしてる」「でも破綻しない」と応えたいです。
つか、若者に向けてそういう風に応えられる国であってほしいですね。
大事なことを書き忘れてた。
年金制度における破綻としてグリーンピアを外すわけにはいきませんね。
制度だけでなくモラルまで破綻してる。
公団なんてのは納付された額と国会の議論を通った税金からの補填を集計して分配するだけでいい。
願わくば、なるべくコストのかからないシステム・組織にする努力を(中の人も外の人もね)。
残念ながらこれは新宿氏に同意できないかも。
そもそも住民税非課税で税金を取っていないのだから、減税しようがない。
「取って配る」くらいなら「最初から取らない」こと、非効率で手間の多い行政を改善すること、年少扶養控除を復活すること、いずれもごもっともです。ただ、所得が少ない世帯に手厚く支援したいというのが今回の給付金の目的なら、減税だけではその目的が達成できないのではないでしょうか。住民税非課税世帯だけをピンポイントにした消費税減税は、テクニカル的に難しいと思われます。
日本国民を「あまねく」支援したいなら「減税」は効果的かもしれません(所得額による濃淡はあるかもしれませんが)。「インフレの影響は住民税非課税世帯以外にも及ぶのだから、住民税額によらず全世帯を対象にすべきであり、やっぱり減税が有効」という反論もあるでしょうけど、それは議論の前提が違います。減税の有効性の前に、「全世帯を対象にすべき!」と声をあげるべきです。
消費税の区分減税と言う手が有ります
主食などを手始めにするのはいかがでしょう
>非効率を好む
D.O.G.E.のメスが入るまで、時間残っていない。
東京大学の東京カレッジ潮田フェロー.元国際通貨基金(IMF)財政局次長,IMFにおいて20年以上にわたり、税椡についての政策と助言の作成・実施を主導した。世界各地の財務省に動言し,40ヵ国以上を訪問,さらにはG20やIMF理事会のために重要文書を執筆したMichael Keenの
「課税と脱税の経済史」を読んだが 世界中の財務省相当機関は いつでもどこでも 同じ行動を取るものだと感じた。
何が不公平かって、税が源泉徴収される種類の投資なら確定申告しなければ所得には何の影響もないこと
株や投信で億儲かってても申告不要なら住民税非課税世帯になれる
投資の利益で健康保険料に影響するのは国保で確定申告する場合だけ
日本は本当にこれでいいのだろうか?
日本の生産性が低いといわれるが、自ら余計な仕事を作り出しているから。職員は効率的な仕事(減税)が分かっているが愚痴を言うと昇級に響く。会社においてトップが無能であれば日産のごときになる。無能(又は強欲)な官僚がまさに日本をダメにしている。
自民党「減税…?そんな事したら利権が…」
事務費の名目で役所にばらまくのが目的ではないのかな
裏取ってないのですが
取って配るのはまだいいが取って配って途中抜くのが問題
そうなんですよ。
非課税世帯とかの線引かおかしいと思うし。税金払ってる世帯もしんどいですしね。おっしゃる通り低所得とか高所得とか関係無く生活がしんどくなって来てる。
高所得世帯は単に物価高也に耐えるチカラがあるだけの話なんですよね。
今までに比べてしんどくなってる=貧しくなってるって事だし。
給付は駄目とか減税は駄目とかでなくて、どちらもやれって話だと思うんですよ。
どうにもこうにもね
東京都の隣設の区役所では住民税非課税世帯だけでなく住民税均等割りのみ課税世帯も支給の対象でした。自治体の考えにより支給条件が変わるのは不公平です。こんな制度だれが考えたのだ。
「取って配る方式」は誰からどれだけ取るか、誰にどれだけ配るかという「判断」が入ります。
「困っている人」を」助けることには反対しにくいのですが、住民税の非課税所帯だけが困っている訳ではありません。
「困っている人」誰もが納得できる判断基準などありませんので、不公平感は必ずあります。
国民の生活支援ならやはり減税が王道なのでは無いでしょうか?
アメリカの景気対策は主として減税でと思うのですが。
”①「取って配る」という非効率を好むのか”
取る部分を変えようとすると税制改正が必要で審議のスケジュールをすっ飛ばすことはできない
一方、給付など配る方は災害対応などと同じく補正予算通すだけらしい
マイナンバーと口座を紐付けした人にだけ支給すれば効率化できるでしょう。
国民全員に配ると言ったら文句を言わないのか?
「やってる風」の仕事のフリした無駄作業
公務員特有という訳ではないが、年金や税を強制的に徴収するのが行政の特質である以上、効率化と合理化は義務といっていい
また、そうでなければ公的機関が存在する意味がない