森永卓郎氏の昨年の著書『ザイム真理教』を読んでみた
森永卓郎氏が昨年5月に上梓した『ザイム真理教』という書籍、少し時間ができたので、一気に読んでみました。当ウェブサイトとして内容に完全に同意するものでもありませんが、総じて「大変わかりやすくて面白い書籍」だといわざるを得ません。なにより、財務省という「カルト集団」を「ザイム真理教」というわかりやすく表現したことは、財務省の増税原理主義の異常性を私たち国民に知らせるうえで有効かもしれません。
森永卓郎氏の昨年5月の書籍
森永卓郎氏といえば「経済アナリスト」として知られていますが、この森永氏が約1年前の2023年5月に上梓した書籍が、『ザイム真理教――それは信者8000万人の巨大カルト』という書籍です(電子書籍だと『ザイム真理教 kindle版』などがあります)。
この「ザイム真理教」、なかなかに興味深い用語を使用しているということもあり、著者自身は「ちょっと読んでみたいな」、と思っていたのですが、「とある事情」からどうしてもこの1年間、時間が取れず、読むのを先延ばしにしてきました。
しかし、ここ数日、ちょっとだけ時間ができたという事情もあり、思い切って時間を空け、一気に読んでしまいました。
ヒトコトでいえば、「面白い」。
これが感想です。
山手線の駅名を冠した怪しげな自称会計士の場合も過去に数冊の書籍を執筆したことがありますが、自身の著書になく、森永氏の書籍にあるのが、「読者をぐいぐい引き込む力」です。読み始めたら止まらなくなるうえに、言いたいことを短い言葉で端的に表現していく力量は、やはり「物書きのプロ」といわざるを得ません。
時事的な話題で予測を外した部分もある
もちろん、「面白い」からといって、内容が100%正しい、というものではありません。
書籍の中で岸田文雄首相について言及している箇所が複数あり、これらのなかで、岸田政権が「財務省の傀儡となった」と断じている記述が確認できるのですが、この点については、少なくとも(森永氏が書籍を上梓後の)この1年の動きを見る限りは、必ずしもその通りとはいえない部分でしょう。
現実に岸田首相は(不十分との指摘はあるにせよ)所得税、住民税の減税を行っているからです。
個人的に、岸田首相の「定額減税」は、減税措置としてはまったくもって不十分だと考えていますし、しかもこれを恒久措置とせず、時限措置に留めた点については、強い不満を抱いている有権者のひとりだと自認しています。
しかし、客観的事実として見れば、岸田首相の指示に基づき、減税が実現したことは事実ですので、この限りにおいて、森永氏が岸田首相を「財務省の傀儡」と決めつけていることは、(結果的には)予測を外していると考えて良いでしょう。
ただし、こうした「書籍上梓後に、書籍に記載した政治家が、書籍の予想と異なる行動を取る」というのは、時事的な話題を書籍に取り込む際に常に出て来る問題点であり、森永氏の書籍の本質的な価値を損なうものではありません。
大蔵省・財務省の体質を体験した森永氏
普段からの森永氏の主張に賛同するかどうかは別として、少なくとも本書に記載されている内容だけで判断する限りは、この書籍に書かれている内容には、経済理論的に正しい部分も多く含まれているのです。
この点、書籍にはいわゆる「MMT(現代貨幣理論)」と呼ばれる「理論」が出て来る部分もあり、MMTに賛同していない当ウェブサイトとしては、若干の不満もないではないのですが、少なくとも森永氏の書籍に出て来る理論のなかで、大きく誤っている部分は見当たりません。
ただ、それよりも説得力があるのが、森永氏が「体験」した、大蔵省・財務省そのものの本質です。
プロフィール文にも記載があるとおり、森永氏は1980年に東京大学経済学部を卒業後、「日本専売公社」(現在のJT)に入社。「管理調整本部主計課」に配属された、という経歴を持っています。
書籍の中では森永氏が当時の大蔵省に呼び付けられ、待機させられたという体験を述べていくのですが、これが自己紹介文にもある、次の記述とも関わっています。
「当時の専売公社はすべての予算を大蔵省(現・財務省)に握られており、『絶対服従』のオキテを強いられることになる」。
森永氏は彼自身が「同部署で体感した大蔵省の実態」を原点に、「ザイム真理教」が生まれ、それが国民生活を破壊していったメカニズムを説明しているのですが、財務省の体質が「カルト」じみているという指摘は、まさに正鵠を射ていると言わざるを得ません。
これにはたとえば、野田佳彦元首相が、民主党が政権を奪取する前には「消費税の増税をしない」と断言していたにもかかわらず、現実に自身が財務副大臣、財務大臣、首相を歴任するなかで変節し、最終的に消費増税に踏み切った様子が描かれているのですが、これに関する森永氏の指摘は秀逸です。
「野田氏の入信はとてつもない政治不信を招いた。『消費税は上げません、シロアリ退治が先です』と言って政権を奪取した政党が、シロアリをますます太らせ、消費税率を2倍にしたのだから、政治を信じろと言われても、何も信じられなくなってしまう」(P35~36)。
ちなみに「入信」とは野田氏が「ザイム真理教」という「カルト教団」の「信者を通り越して、実質的な教団幹部に変貌」(P34)したことを意味します。
また、「シロアリ」とは野田氏が2009年の総選挙の応援演説で「みなさんの税金にぶら下がる天下り法人」に関連して出してきたたとえですので、森永氏の「シロアリを太らせ」の表現には、(野田首相が)「財務省などの利権そのものを拡大させた」ことへの批判が込められていると見て良いでしょう。
いわば、「民主党政権の失敗」は、「民主党の失敗というだけでなく、有権者の政治不信を強めたという点においても大きな失敗だった」、というわけでしょう。
新聞社などに対する批判についても同意せざるを得ない
また、「アベノミクス」を失敗させたのは(野田政権時代に仕込まれた)2度に及ぶ消費税の増税である、といった指摘に加え、この「ザイム真理教」の「強力なサポーター」として、「大手新聞社、富裕層、『最強の親衛隊』国税庁」などが挙げられているくだりもあります。
このあたりについて、当ウェブサイトとしては100%同意するものではありませんが、少なくとも大手新聞社やテレビ局などが「国の借金」、「財政再建の必要性」といった財務省の言い分を垂れ流しているという問題点については、森永氏の指摘どおりでしょう。
その森永氏は昨年末に、ステージ4の膵臓癌であることを公表しているそうですが、改めて快癒をお祈りしたいと思う次第です。
いずれにせよ、この「ザイム真理教」という表現の「過激さ」については、当ウェブサイトの読者の皆さまのなかにも「疑問だ」と感じる方はいらっしゃるかもしれませんが、個人的には、財務省の増税原理主義についてはこの手の「わかりやすい表現」こそ、人々に広めていくうえで有益ではないかと思います。
また、とりわけ大手新聞社、大手テレビ局などが財務省の言い分を垂れ流しているという点については、まったくそのとおりです。
このあたりは先日の『上川発言報道問題で林智裕氏論考が「社会の停滞」警告』などを含め、これまでにずいぶん、当ウェブサイトでも取り上げて来た「メディアの専門性のなさ」の問題とも関わってくるものでもあるのです。
いずれにせよ、官僚支配、メディアの虚報、特定野党などについては、『【総論】腐敗トライアングル崩壊はメディアから始まる』などでも論じてきたとおり、じつは混然一体となった利権の問題でもありますし、最近の「悪い円安」論や「悪い賃上げ」論なども、メディアの専門性のなさを象徴するものでもあります。
その意味では、じつは問題はすべて根っこでつながっているのだ、という言い方もできるのでしょう。
本文は以上です。
金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。
日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。
読者コメント欄はこのあとに続きます(コメントに当たって著名人等を呼び捨てにするなどのものは禁止します)。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。
読者コメント一覧
※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。
やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。
※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。
※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。
当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。また、著名人などを呼び捨てにするなどのコメントも控えてください。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。
コメントを残す
【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました
 | 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |
【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました
 | 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |


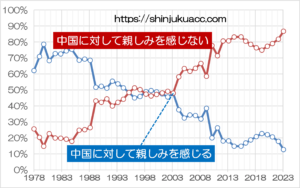
シロアリ…東京都にぶら下がるWPBCはさしずめ「都政のシロアリ」ですね。
>いずれにせよ、官僚支配、メディアの虚報、特定野党などについては、『【総論】腐敗トライアングル崩壊はメディアから始まる』などでも論じてきたとおり、じつは混然一体となった利権の問題でもありますし、最近の「悪い円安」論や「悪い賃上げ」論なども、メディアの専門性のなさを象徴するものでもあります。
うーん、『悪い賃上げ』論を検索してもヒットしないのですが、どんなのがありましたかね?
普段予算にケチケチな財務省が「公金チューチュー」に無反応なのは何故でしょうね(棒)?
夢乃colaboと言いなさい
今話していることってそんなに難しいことなのか。
支出を賄う収入がないので過去の貯えを取り崩しているだけのことではないのか。
日本の場合過去の貯えがたっぷりあるので当分の間は大丈夫。
世界を見渡せば日本のように豊かな国ばかりではなく、そのような国は過去の貯えはなくサラ金から(つまり外国から)借りざるを得ないということではないか。
世の中には収支にうるさい人がいて、毎月収入の範囲で生活するべきだと考えている人たちもいる。それが財政法であり財務省ということ。
>支出を賄う収入がないので過去の貯えを取り崩しているだけのことではないのか。
素朴な疑問として、過去の貯えを取り崩しているのですか?
国家として、過去に「蓄えた」ことなんかありましたか?
金との兌換はとうの昔にやめてます。
通貨の裏付けは「信用(credit)」なのであって、蓄えとの兌換ではありません。
言葉足らずですいません。
「過去の貯え」とは民間(主に家計)の貯えのこと。
第二次大戦時を考えればわかりやすいかも、戦費を税収でまかなえず戦時国債を発行している。この原資は家計にある過去の貯えじゃないですか。これは日本に限らず米、英も同じ。
sqsq様
財務省の最大の悪弊は、政府の銭勘定を国の銭勘定と、わざとだか、それとも頭から信じ込んでいるのか、混同して国民に言いふらすことじゃないでしょうか。
国債にしても、あれは「政府の借金」。ほとんどが国内で消化されているんだから「国の借金」というのはおかしいでしょう。
「民間の貯え」というなら、その膨張は現在進行形。別にそれを取り崩しながらのその日暮らし、「たこ足」経済状態では決してないと思います。
森永氏の経済評論は的を射ていることが多いので、それなりに評価している。
しかし、同氏の近著は、陰謀論も書いてあるらしい。
読んではいない、というか、事前の広告を見て、日航機事故陰謀論が書いてあるらしいことが分かったので、読むのを止めた。
本稿で近著のことを思い出し、アマゾンのその近著の読者コメントを読んでみて、何故陰謀論とも取られかねない日航機事故のことを書いたのかが分かった。
この日航機事故以降、日本はアメリカの言いなりに成らざるを得なくなり、それが、今日の経済低迷の原因である、という所へ持って行きたかったらしい。
日航機事故以前から、戦後の日本はアメリカの言いなりであることは分かっていることなので、この本で日航機事故の陰謀論まで持ち出して来ることは無かったと思う。今日の経済の低迷は、財務省のザイムノイローゼと、それに牛耳られた政治の無策が原因であることは、森永氏の前著で解き明かされているのだから、わざわざ、近著「書いてはいけない」は、本当に書いてはいけなかった。氏の今までの主張に傷を付け疑問符も付けることになったように感じる。
こんな話どお?
毎月100万稼ぐ親父。その中からお母さんに70万円渡しているが家計はその収入では足りず80万円かかる。不足の10万円は親父の過去の貯えを取り崩してお母さんに貸している。
「お母さん、5年前に貸した5万円返してよ」
「はい、もちろん返すけど今度は10万円貸して」
これを繰り返してきたのが日本の財政なのか。
親父の貯えが潤沢なので続けられるけど、お母さんの借りは1000万円に膨れ上がっている。
解決するには①80万円の生活を切り詰めて70万円にする。②毎月渡す金額を10万円増やして80万円にする。親父はどっちもいやだと言っている。
ある年お母さんに臨時収入があった。親父に返すことも考えたが家族旅行に使ってしまった。
(これ岸田の減税)
お隣にKという一家がいる。うちのことを嫌っているけど見栄を張ってうちと同じ生活水準を保とうとしている。K家も家計は赤字だがお父さんの貯えは少ない。しばらくは取り崩していけるかもしれないがそれが尽きたらサラ金に行くしかないと思っている。
ある日いいアイデアが浮かんだ。困ったときはお互い様だから100万円の融資枠を隣と約束できないだろうか。隣はあまり乗り気ではなかったがお隣同士という事でしぶしぶOKしてくれた。(これスワップ)
これ、もう一歩進んだ話にしないと、オチや原因が分からない。
先ず、毎月100万円稼ぐ親父(国民)の稼ぎは、GDPなのか?は、横に置いておいて。
この話の内容からすると、このお母さん(政府)は家計のやりくり上手とは言えないことになる。やりくり上手なお母さんは、キチンと収支は合わせた上に、家族には不満を持たせず、我が家は贅沢はしてないけど、幸せだと家族に思わせられるようなやりくりをする。
しかも、お父さんが、安心して稼げるようにと、何やかにやと気を遣う。質素でも、栄養バランスの採れた食事を用意したり、病気にならないように衛生に気をつけ、ストレスが溜まらないようにして自分の役割はキチンと果たし、ましてや、お父さんが汗水垂らして稼いだお金を流用して自分は散財したり夜遊びをして無駄遣いしたり、隣の旦那(隣国)に流し目を送ったりお小遣い上げたり、なんて、無駄な金を垂れ流したりしない。
ちゃんと自分の旦那さん(自国民)の世話をして、旦那さんの稼ぎが更に増えるようにする。
長くなるので、ここ迄とするが、ここ迄書いただけでも、このお母さん、自分の旦那さんの稼ぎが、更に増えるようなことはしていない。
ましてや、旦那の稼ぎを担保にして、隣の少し足りない奥さんと、貸し借りの約束までするなんて・・・。
いやはや、こんな例え話に置き換えると、ウチの奥さん(政府)、相当に頓珍漢なことやってるようだ。
夫婦間の貸し借りは、母には債務ですが父には債権です。
colabo問題みたいに、母が教団の珍味や壺を買ったなら問題ですが、母がPCを買って手書きより帳簿事務を大幅に省力化したり食洗器やルンバを買って空いた時間で子供の勉強をみたりするなら、まったく問題ないでしょう。
同じ土俵で例えるなら、日本は資産家なのに父がシブチンで母に生活費を少額しか渡さないので、母は未だに薪割して炊事し昭和の家事を強いられている、とか。
節約することと出すもの出さないのとは違いますよ。
予算をつけることとそれが無駄でもよいかも違いますよ。
なんか、根本的なところで違和感があります。
マネタリスト的な
「経済における貨幣流通量は、生き物における血液量」
みたいな考え方は、どう捉えておられますかね。
2008年度の財団法人認可は0軒でした。ところが2011年には2273軒 阿部政権下2014年では9300軒にまで膨れ上がってます。これらは消費税の増税とは無関係なのでしょうか?
これら法人はどうやって収入を得ているのでしょうか?企業では無いので利益活動は行っておりませんので助成金と寄付と考えるのが普通では無いでしょうか・・・・・